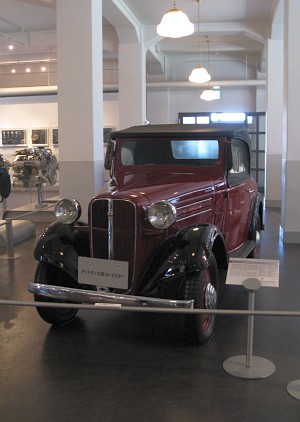茅ヶ崎名物 食べるマンホール
茅ヶ崎名物 食べるマンホール
神奈川県茅ヶ崎市の蓋のデザインをそのままプリントしたゴーフル。

直径約14.5cm。

クリームをサンドしたゴーフルが一袋に3枚入っている。結構な食べ応え。
こちらはゴーフルのデザインの基となっている本物のマンホールの蓋。「烏帽子岩」と「太陽」(朝日か夕日)がデザインされている。
ゴーフルの絵との比較。細部に至るまで忠実に再現されている。

茅ヶ崎駅。東海道線と相模線の駅で、相模線では起点駅になっている。「茅ヶ崎名物 食べるマンホール」は駅ビルLUSCA1階の湘南ちがさき屋にて1袋315円で販売されている。販売元は湘南ちがさき屋本舗で、駅ビルの店を含め茅ヶ崎市内に7店舗を展開しているようだ。ただ、「茅ヶ崎名物」を名乗っているわりにその知名度は低く、観光案内所と駅周辺の菓子屋数軒で尋ねてみたが誰も知らなかった。最後に回った駅ビルでようやく見つけた次第だ。販売元の湘南ちがさき屋本舗ホームページにも記載されていないようだ。もっと評価されていいと思うぞ。


こちらは彩色されていない蓋。彩色されてなくてもカッコイイ。

市章が入った蓋。

基準点の蓋。

なぜか「馬」がデザインされた側溝の蓋。

蓋にもデザインされている「烏帽子岩」。平塚寄りの海岸から南東方向を向いて撮影した。


蓋(ゴーフル)の絵と比べると左右が反転しているように見える。「烏帽子岩」は見る方向によってその姿が大きく変わり、辻堂寄りの海岸から南西の方向に「烏帽子岩」を望むと蓋の構図と同じ姿に見えるようだ。従って、蓋にデザインされている太陽は夕日なのではないかと思われる。

「烏帽子岩」は茅ヶ崎のシンボルとなっており、海岸線の遊歩道の車止めも烏帽子岩を模した形になっている。
以上、撮影は2010年9月。
関連リンク
●この日の管理人のつぶやき(Twitter)
●神奈川県茅ヶ崎市(駅からマンホール:2007/10/27)
●湘南ちがさき屋本舗(販売元)
●おっ!tottoどこ行くの?さん