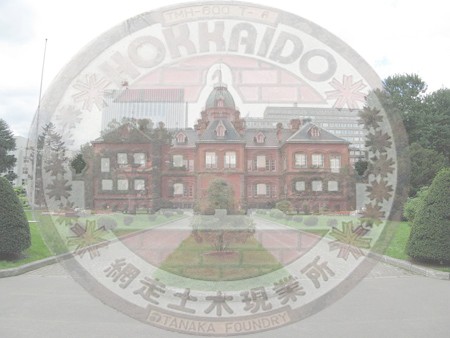東京府豊多摩郡澁谷町(現 東京都渋谷区)
右横書きで、「澁谷町 阻水弇」と書かれた蓋。澁谷町は明治22年に澁谷村として誕生した自治体で、明治42年に町制を施行、その後昭和7年10月1日に東京市に編入されて消滅している。同時に編入された千駄ヶ谷町、代々幡町と共に澁谷區を構成し、そのまま現在の東京都渋谷区の一部となっている。
澁谷町の蓋は現在の渋谷区内ではなく、世田谷区内に所在する駒沢給水所構内に現存している。駒沢給水所は、大正時代の人口増加に伴う水不足を解消するために澁谷町が布設した町営水道「澁谷町水道」の施設の一つで、東京市水道局に移管された後、現在は東京都水道局が管理を行っている。
2002年に結成された駒沢給水塔風景保存会の主催で毎年10月1日の都民の日に「駒沢給水所構内見学会」が実施されており、筆者もこの機会にこの貴重な近代遺産を見学させていただいた。
こちらはやや大きめの蓋。右横書きで「澁谷甼 阻水弇」と書かれている。最初に掲載した蓋とは大きさだけではなく、「町」の字が異なっている。
「町」の字の比較。「甼」は「町」の異字体で、現在ではあまり見られない書き方だ。
駒沢給水所構内では現在再整備事業を行っていて、さらに先日襲来した台風の影響もあり、見学できる箇所が限られていた。この蓋は立ち入りが禁止されている場所に見えた蓋だ。「町」の字は最初に掲載した蓋と同じ字体だが、蓋のサイズはこちらのほうがやや大きい。
こちらは小型の角蓋。「澁水 阻水弇」と見える。他の蓋が右書きであったのに対して、この蓋は左書きになっている。古い蓋を鑑定するうえで右書きか左書きかは重要な手掛かりの一つだが、明らかに戦前の設置である蓋でも左書きのものがあるということは記憶に留めておきたい。
さらに小型の丸蓋も見つかった。こちらは右書きで「阻水弇」と書かれている。上部の紋章は「澁」の字を図案化した澁谷町の紋章だと思われる。
紋章部分を拡大。判りにくいが「止」の字が3つ輪を描き、さらにその外側を「氵」の三本線が取り囲む形状になっている。澁谷町の蓋は駒沢給水所に水を供給していた砧下浄水場の構内にも残っているようで、綺麗な状態の紋章はそちらで確認できるようだ。Oka Laboratory 備忘録さんのページで確認できるので、こちらも是非ご覧頂きたい。(マウスカーソルを乗せると紋章を重ねて表示)
地面から目を離して空を見上げると、中世ヨーロッパの古城を思わせる堂々とした出で立ちの給水塔が見えた。高さは約30m。「澁谷町」と書かれた蓋はどれもこの給水塔近くに現存している。
給水塔は、ここから澁谷町まで送水するため水圧をかける目的で造られており、写真奥の2号塔が大正12年3月に、手前の1号塔が同年11月に完成している(なぜか2号塔が先)。間に関東大震災が発生しているが、二つの塔に大きな被害はなっかたのだそうだ。「澁谷町水道」は大正13年3月に完成しており、今回掲載した澁谷町の蓋もそれまでに設置されたことになる。
水道布設記念碑。手前の池は駒沢給水所の完成時に存在していたが、水道布設記念碑は昭和2年に造られたのだという。この事実は近年発見された資料により明らかにされたということで、それまでは記念碑も駒沢給水所と同時に造られたのだと考えられていたのだそうだ。
こちらは昭和6年11月に着工された第1期拡張工事で建設された第1配水ポンプ所。スクラッチタイルが張られ、アールデコ調の装飾も施されており、格調高い造りになっている。
上の写真で第1配水ポンプ所の階段下に見えた蓋。縁石に囲まれているが、蓋自体は無地の単調なものだ。もしかするとどこかの時点で交換された蓋なのかもしれない。
第1配水ポンプ所の内部。年に1回、見学会の実施されるこの日にしか扉は開かれない。
内部を保護するため窓は全て塞がれているが、もともとは全てガラス窓で、内部はとても明るかったのだという。
ポンプ所の内部に設置されている蓋。この蓋もポンプ所が造られた昭和7年に設置されたものだと思われる。網目模様は現在の東京都水道局の蓋のデザインにも通じている。
ポンプ所の周辺には他にも古い蓋がいくつか確認できた。この蓋には右書きで「排氣弇」と書かれている。また、東京市章(現在の東京都章)を基にしたと思われる亀の子模様も古さを感じさせる。第1期拡張工事の途中で澁谷町は東京市に編入されているので、この蓋は東京市になってから設置されたものなのかもしれない。
立ち入り禁止区域にも古い蓋はまだまだありそうだった。こちらは半分土に埋もれた「排水弇」の蓋だと思われる。
こちらはベンチュリー・メーター(量水計)が格納されていた建物(量水計室)。給水塔と同時期に造られた建物で、老朽化のため長らく内部に立ち入っての見学はできなかったそうなのだが、当時と同じ材料と様式で改修され、今年から見学が可能になっている。
こちらがその量水計室の内部。屋根の部分はヒノキで造られている。
駒沢給水所から渋谷方面を望んだ写真。現在は閉鎖されている門からは水道道路がまっすぐ続いており、正面には三軒茶屋に建つキャロットタワーが見える。
上の写真の左下に見える蓋。流量計と書かれた蓋だが、こちらはだいぶ新しそうな蓋だ。駒沢給水所の給水所としての機能は平成11年10月に停止しているので、この流量計も現在は使われていないものと思われる。駒沢給水所は現在、災害時の給水拠点として利用されており、配水塔内部では現在でも水を循環させ綺麗な水を保持しているのだそうだ。
こちらは渋谷とは逆方向、砧下浄水場へ続く水道道路。水道道路の散策も面白そうだ。
関連リンク
●この日の管理人のつぶやき(Twitter)
●駒沢給水塔風景保存会さん
●ZERO SPIRITSさん(筆者も写ってる!)
●Oka Laboratory 備忘録さん
●Kousyoublogさん
●世田谷の川探検隊さん