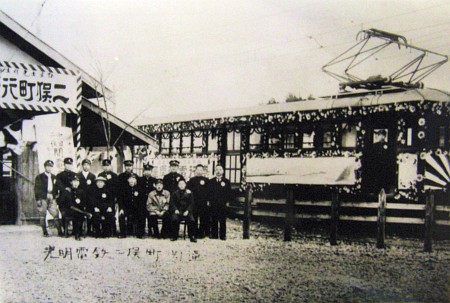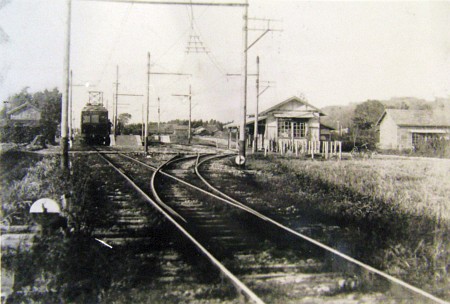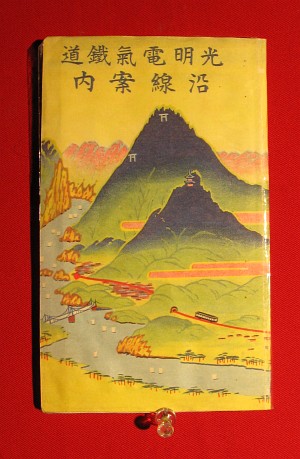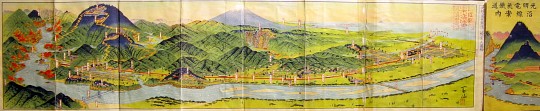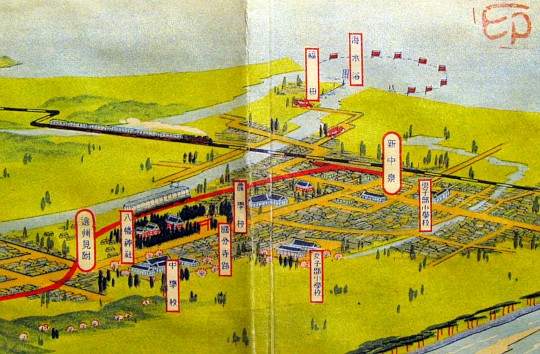旭テック環境ソリューション株式会社
旭テック環境ソリューション株式会社(以下、旭テック)は、主に上下水道関連製品を製造・販売している会社で、鉄蓋業界では大手だ。静岡県菊川市に本社を置いており、先日の静岡○ごとワイド!の収録の際に大変お世話になった。
今回の記事では、趣味の幅を広げるべく、いつものように地方の蓋と特色を紹介する形ではなく、鉄蓋製造会社という括りで鉄蓋を観察・鑑賞することにしてみた。
本社のショウルームには彩色された蓋が幾つか展示されていた。平日のみだがショウルームは一般に公開されている。役所や下水処理場などでこういった蓋の展示がされていることもあるが、製造会社のショウルームという穴場もあることを知った。機会があれば他の製造会社のショウルームも覗いてみたい。
ここに展示されている蓋はほぼ全て静岡県内の自治体のものだが、旭テックは全国規模の企業なので、その製品も日本全国で見ることができる。ただ、さすが地元だけあって、静岡県内の自治体での採用率はかなり高いようだ。
こちらは旭テックのお膝元、静岡県菊川市の蓋だが、デザインの構成や製造は旭テックが行ったのだそうだ(キャラクターデザインは御当地出身の漫画家、小山ゆう氏による)。実はこの蓋、製造会社という切り口で観察すると、いくつかの特徴が見えてくる。
1つ目の特徴は、蓋の上部にあるこの部分。蓋の裏側のこの部分に蝶番があるため強度が必要で、蓋の図柄に関係なく厚くなっていることが多い。旭テックの製品では、この厚い部分はやや細長く、下端が丸くなっていることが多い。
比較の為に他社製品の蝶番部分を並べてみる。左は日之出水道機器、右は長島鋳物の製品だ。日之出水道機器の製品では下端が四角く、中央に長方形の窪みが入っていることが多い。一方、長島鋳物の製品では旭テックの製品と同じく下端が丸くなっているが、比較的幅が広くなっており、上部に縦スジが入っていることが多い。
2つ目の特徴は、蓋の下部にある鍵穴の部分だ。旭テックの製品ではキノコのような形になっており、鍵穴の蓋部分にはネジが見える。
他社製品との比較。左の日之出水道機器の製品は鍵穴が縦長で、鍵穴の蓋部分には隙間がなく、小石や異物が下に落ちないようになっている。一方、右の長島鋳物の製品では鍵穴は小さく、上部に半円状の窪みがあることが多い。
3つ目の特徴は受け枠の部分だ。旭テックの製品には、落花生のような模様がデザインされている。
他社製品との比較。上の日之出水道機器の製品では、くさび形の模様が並んでいる。一方、下の長島鋳物の製品では、平行四辺形が並んでいる。
これらの特徴を覚えておくと、各地方のデザイン蓋について、その製造会社を推測することができる。そんなこと知って何の役に立つのか、恐らく何の役にも立たないとは思うが、誰も知らないようなことを詳しく知っているということそれ自体が楽しい。
次に、旭テックの製品に使われる汎用的なデザインに注目してみる。この蓋は先日紹介した静岡県中伊豆町の蓋だが、この蓋のデザインは旭テックが考案したもので、全国で使われている。太陽のような模様で、鍵穴の形状も特徴的だ。
こちらは日坂宿(静岡県掛川市)で見つけた親子蓋になっている蓋だが、親蓋には先に紹介したのと同様の太陽のような模様が入っており、子蓋の蝶番部分と鍵穴部分には旭テックの製品らしい特徴が見られる。
親蓋についても他社製品との比較をしてみる。左の蓋は日之出水道機器の製品で、亀甲模様になっている。一方、右の長島鋳物の製品では、三角形を基調にした模様が並んでいる。これらの模様はそれぞれの製造会社が考案した模様なのだが、後日またそれぞれ独立した記事で詳しく紹介するつもりなので、ここではこの程度の記述に留めておく。
この蓋も日坂宿(静岡県掛川市)で見つけた小型の蓋で、同じく太陽のような模様だ。
こちらは静岡県竜洋町で見つけた手毬のような模様の小型の蓋だが、こちらも旭テックの製品ということだ。
こちらは旭テック本社の敷地内で見つけた蓋。社内の敷地だけあって、さすがに自社製品を使っている。下部には社章と社名も入っている。
こちらは静岡県掛川市で見つけた上水道関連の蓋。上水道関連の蓋についてはまだあまり分類を進めていないのだが、この蓋の右下に社章が入っているので旭テックの製品ということがわかった。
こちらは静岡県磐田市で見つけた比較的新しい蓋。滑りにくいよう工夫された模様になっており、鍵穴の部分に旭テックの製品らしい特徴が見られる。
こちらも静岡県磐田市で見つけた蓋。ゾウリムシがマイム・マイムを踊っているような模様になっている。鍵穴部分と受け枠に旭テックの製品らしい特徴が見られる。
こちらは下水道展’10 名古屋に出展していた旭テックのブース。いろいろと質問に答えていただいた上に、素敵な扇子まで頂いた。
旭テックのブースには、次世代高品位の鉄蓋が展示されていた。先に紹介した磐田市の蓋と同じもののようで、既に路上に設置され始めているようだ。
こちらも旭テックの製品で、下水道展’10 名古屋の次世代型高品位グラウンドマンホール推進協会のブースに展示されていた。蓋の上部に旭テックの社章が入っており、旭テックの製品であることは一目でわかる。また左下には製造年(10: 2010年)と耐重量の規格(T-25)が記されており、蓋を開けなくても蓋の詳細がわかるようになっている。これらは次世代型鉄蓋の特徴のひとつなのだが、それらについては後日独立した記事にまとめる予定だ。
最後に、なかなか見る機会のない蓋の裏側について。ロケで旭テックの本社にお邪魔したときに見せていただいた。支持構造が放射状になっているが、これも次世代型鉄蓋の特徴のひとつだ。また、蓋の裏にも幾つか情報がある。
上から、製造元を示す社章と社名、材質を示すFCD700(Ferrum Casting Ductile: ダクタイル鋳鉄)、耐重量規格を示すT-25、径を示す600(O)、製造年を示す10(2010年)と日本下水道協会の認定標章が記されている。
以上、今回は旭テック環境ソリューション株式会社の下水道向け鉄蓋製品について纏めてみた。記事に纏めるのが普段より格段に大変だったが、他所には無いマニアックな内容になったのではないかと思う。今後も月に1回くらいの割合で鉄蓋製造会社や汎用的な地紋について掘り下げて書いてみようと思うので、マニアックすぎると逃げずに今後もお付き合い願います。
関連リンク
●静岡○ごとワイド!(駅からマンホール:2010/09/09)
●静岡県(小笠山総合運動公園)(駅からマンホール:2010/10/12)
●静岡県菊川市(駅からマンホール:2010/10/13)
●静岡県掛川市(駅からマンホール:2010/10/25)
●旭テック環境ソリューション株式会社