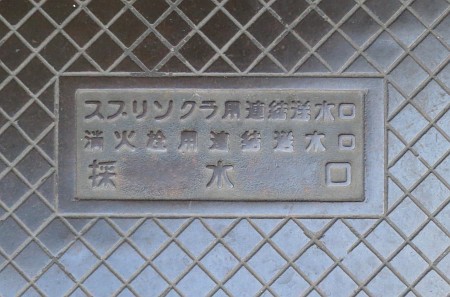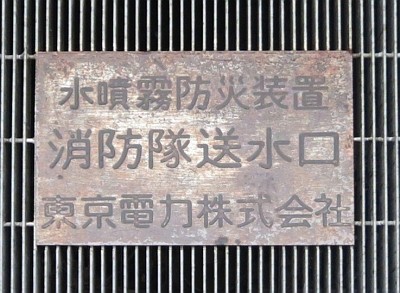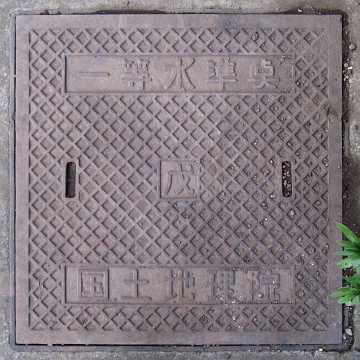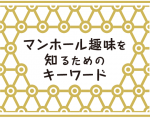茨城県のデザイン蓋が集結 ~ 県庁本庁舎の鉄蓋展示
茨城県庁本庁舎の鉄蓋展示
下水道展に工場見学に送水口ナイト、そして次はマンホールナイトとイベント続きで更新が進まず、当ブログへお越しいただいている皆様にはご迷惑をおかけしてしまっている。下水道展のレポート、その際「デザインマンホール100選」の著者、池上修さんに案内していただいた大阪・滋賀のたくさんの蓋の紹介、中途半端に終わっている中川水循環センターで展示されている蓋の紹介などなど、書きたいこと、書かねばならないことは山積みなので、もっと頑張らねばと思っている。
気がつけばもう9月10日の下水道の日は目の前で、既にイベントを開催している自治体もあるようだ。今回はそんなイベントの一つ、茨城県庁本庁舎の鉄蓋展示について取り急ぎレポートする。展示は既に始まっていて、茨城県庁舎の1階の中庭と、2階の県民情報センターで行われている。筆者が訪問したのは日曜日で閉庁日だったため、1階の展示は上から眺めるのみだった。また、2階の展示(鉄蓋やデザイン画等)についても展示は9月1日午後からとのことで、まだ始まっていなかった。しかし、中庭に並べられた25枚のデザイン蓋は圧巻で、非常に見ごたえのある展示になっている。
以下、筆者の独断で、目をひくデザインの蓋を幾つか紹介してみる。
茨城県行方郡麻生町(現 行方市)
「霞ヶ浦」の大きな「コイ」と「ヨット」がデザインされている。twitterで教えていただいたが、「鯉こく」は霞ヶ浦沿岸の郷土料理となっているのだそうだ。
なお、蓋の下部にある「あそうまち」の隣の記号のようなものは、麻生町の町章だ。
茨城県行方郡牛堀町(現 潮来市)
葛飾北斎の「富嶽三十六景」のひとつ、「常州牛堀」がデザインされている。富士山をデザインした蓋は数が多いが、恐らくこの牛堀町の蓋が富士山から最も遠いところにある蓋なのではないかと思われる。
この蓋は金色で彩色されているようだが、できれば北斎の「常州牛堀」と同じ色で彩色された蓋も見てみたい。(† Wikipediaより取得。作者:葛飾北斎、利用許可:パブリックドメイン)
茨城県那珂市
市の花「ヒマワリ」がデザインされている。先に紹介した麻生町の蓋のデザインもそうだが、大胆な構図で、それでいてスリップしにくそうなデザインでもあり、本当に素晴らしい。
ちなみに、那珂市は2005年1月に瓜連町を編入合併するまでは那珂町だったが、その時代も町の花は「ヒマワリ」で、蓋のデザインも当時から同じものを使っているようだ。那珂町の木は「スギ」だったが、合併後瓜連町の花・木であった「ヤエザクラ」を市の木として制定している。瓜連町の蓋にはその「ヤエザクラ」が以前より用いられていたのだが、そのデザインは今も引き続き那珂市瓜連地区の蓋に使われているようだ。マンホールの蓋のデザインを元に市の花・市の木を選んでいたりして。だとしたら面白い。
茨城県結城郡八千代町
温泉有り、バーベキュー・キャンプ場有りのレクリエーション施設、「八千代グリーンビレッジ」の風景がデザインされている。マンホール蓋のデザインにその町ご自慢の風景を使う点は非常に好感が持てる。
鉄蓋展示が開催されている茨城県庁本庁舎。水戸駅南口から出ているシャトルバスを利用するのが便利。
こちらは1999年まで本庁舎として使われていた歴史ある旧本庁舎の模型。現在も三の丸庁舎として利用されている。水戸駅から徒歩で行ける距離にあるが、この庁舎で鉄蓋展示は行われていないのでご注意を。
本庁舎25階の展望ロビーからの眺望。偕楽園の方向を望む。条件がよければ筑波山はもちろん富士山やスカイツリーも見ることができるとのことだ。展望ロビーは閉庁日でも利用できるので、本庁舎まで来たら是非足を伸ばしてみていただきたい。なお、展示は9月11日までの予定。
関連リンク
●この日の管理人のつぶやき(Twitter)